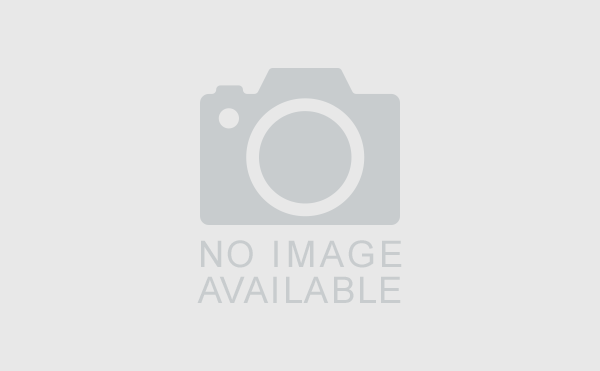上林エレーナ幸江先生(責任著者:羽賀博典先生 / 岡島英明先生)の論文が発表されました。
小児外科助教 上林エレーナ幸江(責任著者:羽賀博典先生 / 岡島英明先生)の論文が、 Liver Transplantation 誌 に掲載されました。
Thirty-year follow-up of immunosuppression modulation: Impact on graft fibrosis and anti-HLA antibodies after pediatric liver transplantation.
Uebayashi EY, Okajima H, Uno S, Kadohisa M, Yamamoto M, Ogawa E, Okamoto T, Okumura S, Ogiso S, Ito T, Takeuchi Y, Hirata M, Yamada Y, Minamiguchi S, Hatano E, Haga H.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40793997/
小児肝移植は生命予後を大きく改善する一方で、免疫抑制療法の長期管理が課題とされています。本研究では、1990年から1994年に京都大学で生体肝移植を受け、移植後30年以上にわたり同一グラフトで生存し、当院で長期フォローアップされている小児レシピエントを後方視的に解析しました。明らかな拒絶反応がみられない場合にのみ、数年をかけて段階的に免疫抑制剤を減量しました。免疫抑制剤を完全に中止できた症例を複数認めましたが、一部の患者ではその後に移植肝の線維化が進行し、免疫抑制剤の再開が必要となりました。再開群では細胞性拒絶反応を示唆するリンパ球浸潤は認められなかったものの、ドナー特異的抗体が陽性の例が多く、抗体関連拒絶反応の関与が示唆されました。継続群では肝線維化の程度にばらつきがあり、晩期のT細胞性拒絶も散見されました。また、抗HLA抗体陽性例は全体として高度線維化と有意に相関していました。免疫抑制離脱群における良好な組織学的・免疫学的所見は、長期的免疫寛容の可能性を示唆する一方、再開群でみられた線維化進行は、慢性抗体関連拒絶に対する従来の免疫抑制戦略の限界を示しています。肝移植は動的なプロセスであり、長期に肝機能が安定している患者においても、組織学的再評価が必要です。