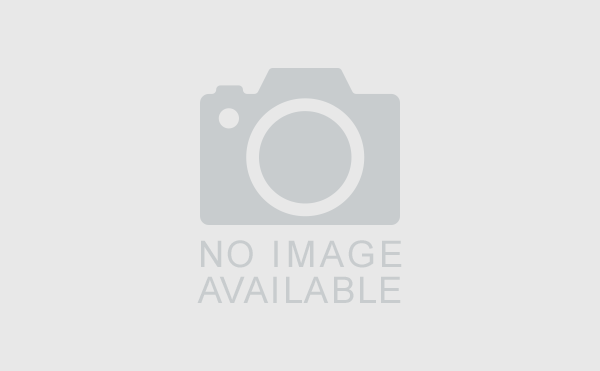教室コラム #16 手術を教える, 教わる 「言語化」と「見て盗め」の間. 前編
手術を教える, 教わる「言語化」と「見て盗め」の間. 前編
石井 隆道
はじめに
手術はよくアートやサイエンスに喩えられますが,むしろ工業製品のようなものだと私は思っています.つまりどこで誰が行ってもある基準以上の,均一な品質が担保されていなければなりません.そのためには携わる外科医全員が手術に関する知識を共有している必要があると思っています.このコラムでは,手術に関する知識や記憶が哲学の認識論や言語論,脳科学でどのように考えられるのか,そしてそれを多くの人に共有するためにはどのようにしたら良いのかを個人的な意見を中心に書いていきます.
言葉にできる知識・できない知識
手術を知っているとはどういう状態でしょうか.禅問答ではなく,具体的な,たとえば肝右葉切除を知っているとはどういうことでしょうか.手術という作業は非常に多くのステップで成り立っています.例えば手指や手術部位の消毒法や手術器具の名前,手術手技の基本操作やその順番,トラブルの対処法などなどです.でもこれらを全て知っていれば手術を最後まで行うことができるでしょうか.この場合,「知っている」とは「できる」を含んでいることになります.
知識にはいろいろな種類があるとされています.その一つは宣言的知識と呼ばれるもので,例えば「日本の首都は東京である」「直で有鉤の鉗子をコッヘル鉗子と呼ぶ」「総肝動脈は腹腔動脈幹から分岐する」といった事実や原理などに関する知識です.命題的知識と呼ばれたり記述的知識と呼ばれたりしており,意識的に学習され,そのほとんどが言語化可能です.というより言語化と密接に結びついています.
一方で,自転車の乗り方とか泳ぎ方のように作業に密接に関与している知識があります.自転車に乗れる人が乗れない人に教える場合に「サドルに跨ってペダルを回すように漕いでください.右に倒れそうになればハンドルを軽く左に曲げてバランスを取って,徐々にスピードが上がってくれば自転車は安定します・・・」と伝えてもすぐに乗れるようになりません.この種類の知識を手続き的知識と呼び,手術に関する知識の多くは手続き的知識に属します.手続き的知識の特徴として,一部は言語化が可能ですが作業の核心になればなるほど言語化が困難になり,知識の行使は無意識的です.すなわち手術の知識を共有したくても,その核心あるいはコツといった内容は無意識的に行われていて言語化が難しいため,マニュアルなどの言葉での説明では伝えきれないことになります.
解像度を落とす「言語化」
それでも無理に言葉にするとどうでしょうか.見当たり捜査というものがあります.これは容疑者などの似顔絵や顔写真を覚えた捜査官が,繁華街などで顔や特徴から容疑者を見つけるという捜査手法です.捜査官は顔の特徴を「キツネ眼」や「団子鼻」などの言葉で覚えるのではなく,顔そのものを映像として覚えるようにしているそうです.一方でソムリエはワインの香りをダークチェリーやスミレ,枯葉,猫のおしっこなどの言葉で表現するようです.これらを考えてみると,感覚や表現の解像度は「嗅覚」<「言語」<「視覚」ということになるでしょうか.そして手術知識の多くは視覚情報ですのでこれを無理やり言語化すると解像度を落として表現することに他ならないのです.
脳はどう覚えているのか?
これまで認識論や言語から手術知識と言語化との話をしました.思弁的な理屈の話でしたが,では人間の脳はどのようにこれらの知識を扱っているのでしょうか.知識そのものを考えることは難しいので,知識をどのように記憶しているかについて考えてみます.宣言的知識(命題的知識,記述的知識)の記憶に該当するのは宣言的記憶あるいは陳述的記憶と呼ばれます.言葉にできる記憶で意味記憶とエピソード記憶に分かれます.事実と経験を記憶するもので,言語化が可能です.頭で覚えるというもので,教科書で学ぶような内容もこの種の記憶になりますが,忘れやすく,一方で反復的に使えば長く覚えることができます.脳では側頭葉の海馬と大脳皮質に記憶されます.
一方で手続き的知識に該当する記憶は手続き的記憶と呼ばれます.言語化できない非陳述的記憶に分類され,言葉にしなくても無意識的に記憶を呼び出すことができ,一度覚えると忘れることがほとんどないことが特徴です.身体で覚えるという状態です.手続き的記憶は大脳基底核や小脳で記憶され,宣言的記憶とは記憶する脳の局在までもが異なっています.宣言的記憶と手続き的記憶の質の違いが,このことでもよく分かります.手術の記憶に関しては,初めのうちは宣言的記憶に止まりますが,数をこなしていくと手続き的記憶となります.手術の基本動作,例えば糸結びも最初は考えながら手を動かしていたものが,慣れてくるとよそ見をしたり目をつぶっていても結紮できたりするようになります.一連の手術操作も同様です.またいわゆる直感や勘が働くというのは手続き的記憶が無意識に呼び出されて危険を事前に察知でき,危険な操作を無意識的に避けるようになったものと思われます.このように手術に関する記憶は宣言的記憶から手続き的記憶へと昇華させ,考える前に手を動かしたり危ない操作を避けたりできるようになれば,迅速かつ安全に手術が行えるのではないでしょうか.
やっぱり「見て盗め」しかないのか
手術に関する知識は手続き的知識でありそもそも言語化が難しいこと,手術の知識は多くが視覚情報であり言語化すると解像度が落ちること,そして手術は身体で覚える記憶である,という話をしてきました.これらのことを考えると,手術の知識を共有するためには今はやりの「言語化」「マニュアル化」「定型化」は馴染まず,昔ながらの「見て盗め」や「背中を見て覚えろ」といった世界もある意味では正しいのです.言葉はいらない,やっている手術をそのまま覚えろ,そして繰り返し練習しろ,です.私の研修医や若手時代にはこのような雰囲気が若干,いや色濃く残って,というよりこの雰囲気そのままで育ってきたので,個人的には決して嫌いではないのですが,しかし旧来の「見て盗め」は非常に効率も悪く,若手への印象もあまりにも悪く,令和の時代には馴染まない方法です.
言語化が難しい手術知識を,「見て盗め」メソッドを封印した上で,分かりやすく丁寧に共有するためにはどうしたらいいでしょう.この問題を解決する一助として,言語と視覚情報が高度に融合した芸術である漫画を参考に,知識の共有や教育の手段としての手術イラストを考察し,その可能性について考えました.手術ビデオが容易に録画記録される時代でも,なお手術イラストを重んじるのは,そのイラストに術者の手術操作に関する認識や考え方が表現されていると思うからです.
(以下後編に続く)